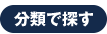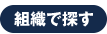甦る古代金堂 慧日寺金堂の復元【第16回】 金具・須弥壇の漆塗り

建築に用いられる金具・金物には、釘や鎹(かすがい)など構造用の金物と、装飾を主な目的とする金具があります。復元金堂にもさまざまな金具や金物が用いられていますので、その一部を紹介します。
構造用金物
長押を留める和釘や床板を取り付ける目鎹(めかす)などがあります。柱を繋ぐ頭貫(かしらぬき)は大釘を打ち込んでいます。
 長押を留める和釘 長押を留める和釘 |  床板の目鎹(めかす)釘 床板の目鎹(めかす)釘 |  頭貫(かしらぬき)を固定する大釘 頭貫(かしらぬき)を固定する大釘 |
飾金具
一口に飾金具といってもさまざまな種類があります。例えば、垂木・隅木などの木口(こぐち)に打つ木口金具、扉の軸元の補強を兼ねた八双(はっそう)金具や藁座(わらざ)金具、長押や扉板を留めた釘を隠すための釘隠しなど種々におよびます。また、立体的な装飾金具の代表に風鐸(ふうたく)が挙げられます。
風鐸(ふうたく)
 《参考例》 平城宮朱雀門の飾金具 《参考例》 平城宮朱雀門の飾金具 |  徳一廟の石層塔 徳一廟の石層塔 |
仏堂の軒を飾る代表的な飾金具である風鐸(ふうたく)。風鈴を大きくしたような形状で、復元金堂にも、隅木の先端に下げることにしています。その音によって魔除けの役割を果たすともいわれており、仏堂の重要な飾金具の一つでした。
慧日寺跡に建つ徳一廟は平安時代の五層の石塔ですが、笠石の四隅には風鐸(ふうたく)を下げたと思われる孔(穴)が開けられていることが判っています。金堂と共に、往時は風になびいて美しい音を奏でていたのでしょう。
須弥壇の漆塗り
漆は非常にデリケートであるため、仕上げまでには多くの時間と手間を要します。まず、本格的な漆塗り作業に入る前には下地作業が必要となります。この下地作業は、素地を強固にしてやせを防ぐと共に仕上げを美しくするための重要な工程で、大まかには次のような順序で行います。
- 「木固め」素地に直接生漆(きうるし)を摺り込んで丈夫にします。
- 「刻苧(こくそ)」刻苧(こくそ)漆と呼ばれる漆を埋め込んで補強します。
- 「布着せ」糊漆を使って麻布を素地に貼っていきます。
- その上に「地付け」といって砥粉(とのこ)や少し粗い地の粉を漆と水で練り合わせたものをヘラ付けします。
- その後、砥粉(とのこ)・生漆(きうるし)・水を混ぜ合わせた「錆」と呼ばれるものを摺り込む「錆付け」を行います。
こうした下地作業を経た後、十分な乾燥養生期間を設けて、ようやく漆塗り工程へと進んでいきます。ここから鏡面のように仕上げていくには、さらに下塗り・中塗り・上塗りを重ねた上に、生漆(きうるし)を摺り込んで研磨する「摺漆」という工程を繰り返しようやく完成を迎えます。

![]()

「刻苧(こくそ)」を埋めて補強 麻布を貼った「布着せ」
![]()

砥粉(とのこ)・地粉を繰返し摺り込む