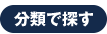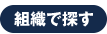甦る古代金堂 慧日寺金堂の復元【第12回】 現地組み立て その6

床張り
8月中旬から行われていた内部の床張りが、約1ヶ月をかけて9月中旬に終りました。
幅一尺二寸、厚さ二寸程のヒノキの板を梁行き方向(正面から見て縦方向)に張っていくものですが、継ぎ目の微妙な段差にはヤリ鉋(がんな)をかけて、あたかも一枚板のような見事な板張りに仕上げら れました。


柱周りの仕上げ 床板はメカス釘で根太に留めます


一枚板のような仕上げ 床張り後の堂内
須弥壇(しゅみだん)
復元金堂は、丈六(じょうろく)薬師坐像が安置されていたことを想定して設計・施工が行われています。丈六とは16尺で、メートル法に直すと約4.8m。これは通常立像の像高を示しますので、坐像にすればその半分の2.5m程度になります。近世の記録では三尊形式であったことが知られていますので、創建当初も脇侍(わきじ)として日光・月光菩薩像が並んでいたのでしょう。とすると、こうした仏像を安置した須弥壇自体も、相当の大きさであったことが想定されます。
復元に際しては幅約7.5m、奥行き約2.5m規模の須弥壇を設置することにしています。表面は黒漆塗り仕上げとなり、現在、建物工事と併行して漆塗りも行われています。


復元金堂の須弥壇には地元会津の漆も用いられます(掻(か)き取りが行われた若松市内の漆の木)
塗りの下地作業である「布着(ぬのぎ)せ」と呼ばれる工程


下地の麻布(あさぬの) 米糊(こめのり)と漆で麻布を貼り付けます
屋根板葺き
9月末から、いよいよ屋根板の葺き上げ作業が始まりました。最初に軒付けの部分から着手し、徐々に上方へと葺き上げられていきます。およそ3万枚もの屋根板をすべて葺き上げるには2ヶ月以上かかる見込みですが、年内には見事なとち葺き屋根が完成する予定です。


とち葺きが始まった軒付け部 軒付けには9枚ものとち板が重なります

軒先を見上げた状態