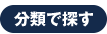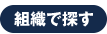甦る古代の伽藍 慧日寺中門の復元【第5回】 木工事 その3 壁工事-中塗り
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

屋根
棟木(棟桁)・母屋桁・軒桁(丸桁)が設置されると、軒廻りの工程へと進みます。垂木は八脚門の類例にならって、二軒(ふたのき)の繁垂木(しげだるき)としました。また、切妻屋根の両端の納めには「破風板(はふいた)」が設置されました。


間隔を密に打つ繁垂木 南北の垂木は棟木上で栓打ちして繋ぎます
破風(はふ)
屋根の妻の納まりのために合掌形に組まれた厚めの板で、破風板ともいいます。写真(左下)に見るような下に反った形が一般的で、これは「照り破風」と呼ばれます。破風板の丈は建物の年代を推定する手がかりとなり、一般に時代が古いほど丈が低めとされます。


左端の山形に組まれたものが破風板 棟木上で合掌形に組み合わされます


垂木上に貼った化粧板 化粧屋根裏の眺め
垂木打ちが完了すると、その上から化粧板が打ち付けられ、さらに飛檐垂木(ひえんだるき)が継がれていきます。

飛檐垂木の設置
壁工事
8月下旬から9月初めにかけて、壁の中塗り作業が行われました。この後しばらく乾燥養生期間をおいて、最後に漆喰仕上げが行われる予定です。
班直し(むらなおし)
荒壁の乾燥後、中塗りに入る前に「班直し」と呼ばれる工程が行われました。まず、格子の上に麻布や寒冷沙(かんれいしゃ)を貼って格伏土(こうふせど)を塗ります。荒壁面を平滑にし、中塗り土とのからみを良くします。また、「散り廻り(壁とその周辺材との境目)」にはひげこや布連(のれん)などの下地材を打って、散り廻り土を塗り付けます。こうすることによって、壁土の収縮による割れや剥がれ、隙間を防ぐことができます。


布連の打ちつけ 散り廻りの処理

中塗り作業の様子
甦る古代の伽藍 慧日寺中門の復元シリーズ
- 第1回 基礎工事
- 第2回 復元中門の仕様・立柱・壁工事
- 第3回 木工事 その1
- 第4回 木工事 その2
- 第5回 木工事 その3 壁工事-中塗り
- 第6回 壁工事-漆喰仕上げ、屋根葺き工事
- 第7回 屋根葺き工事
- 第8回 中門復元工事竣工