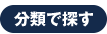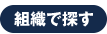尾寺のはなし/磐梯町の伝説と昔話
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新
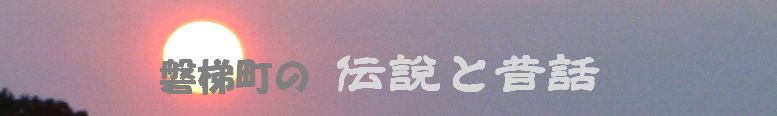
尾寺のはなし
大昔、磐梯山には大蛇が住んでおって、磐梯山の回りをぐるぐると巻いて、七回り半もあったそうだ。
その時の大蛇の頭は「とう寺」 にあって、尻尾が今の「大寺」 のあたりにあった。
そこに寺を建てたので「尾寺」 と呼び、やがて「大寺」 になり,
「とう寺」 は「頭寺」 と呼ばれていたが、いつの頃からか「塔寺」 になった。
梵字清水(ぼんじしみず)のはなし
大同二年に、磐梯山が荒れて人々を困らせたので、都から弘法大師様がお出になった。
この山の荒れを鎮めるために、「稲荷原」 に立って祈り、
磐梯山の鎮めのために寺を建てる場所を探してもらうことになり、
お持ちになってい三鈷を空中に投げ上げたところ、雲の中に消えていった。
その後、大師は方々を訪ね歩いて、今の梵字清水のあたりに差しかかったところ、
梵字のような形をした雲が北西に流れていくのを見た。
大師は、その梵字の形をした雲の流れる方に行って尋ねたところ、
今の磐梯神社のうしろ、閼伽井の側の藤の枝に三鈷が引っ掛かっているのを見つけた。
そこで、その地に寺を建てたという。