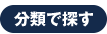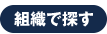厩嶽山馬頭観音 3/磐梯町の伝説と昔話
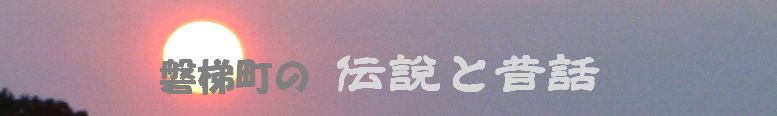
厩嶽山馬頭観音 3
ときは天平年中、聖武帝の頃、
高僧行基は天皇の命をうけて全国をまわり、水利のわるいところには水利の便を、 洪水で困る地方には堤防の築き方や橋のかけ方を教えて歩きまわり、 地方の農民からは生仏としてしたわれました。
その行基が当国にまいり一夜の宿をとったのが源橋村のある一軒でした。
その夜の寝につくと、いななく駒の声がするので山中深く進んで行くと、猿が七匹の駒をひき走るさまは飛ぶ鳥の如く天空を行くようでした。
その葦毛の駒には一人の老翁が跨り、むちをあげて行基を招きました。
「我は天満の星である。
この山に長く住んでよく六道(六種の迷界・地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上)の中において
ながく病馬の苦悩を直して来ました。
然しこの峰つづきの猫魔ケ嶽に悪霊どもが、我が修業のじゃまをしてならない。
汝ははやくこの山を開いて末世の諸願を成就し六道に迷う者どもを救ってください」
と告げ、駒のいななきとともに消えうせてしまいました。
夢からさめた行基は身を潔斎し、
一刀三礼(仏像を一彫りするごとに掌をあわせて三礼する)をしながら馬頭観音の像を彫刻し、
山頂に一字をたて安置し、厩嶽山と名前をつけました。
この地方の人々は農耕馬の無病を祈願するために祭礼の前日から列をなして参詣致しました。
また駒の健康にあやかって当年二歳の子を背負って急坂険路を登ってお参りしたのです。
やがて山が険しく登るのに難儀であるということから、前建を木流村と源橋村の外柴に移して参詣を視易くいたしました。
祭礼は四月八日・六月十六日、馬がこの日に参拝すれば馬に怪我なしといわれ、馬を引いて、または乗馬で参拝したものです。