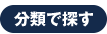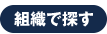黄金の駒/磐梯町の伝説と昔話
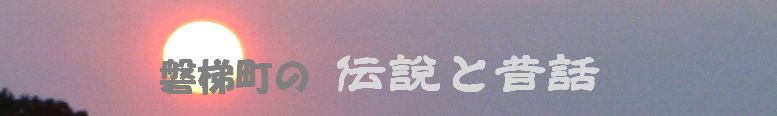
黄金の駒
むかし、いつのころか磐梯山の北側のふもとに、雄子沢という村がありました。
その村には倉吉という若者がおり大変漁がすきで、毎日のように釣りをしては、その日を送っていました。
特に磐梯山の中腹にある御鏡沼を、またとない釣り場としており、
また、この沼は広さ数百米碧に澄んだ水は天を写し、はかり知れない程の深さで、
周囲は数百年の大木が枝をのばし昼でもひっそりとして、そら恐ろしい沼でした。
雄子沢村の人々は、魔性の主が住むといって誰も近づきませんでした。
倉吉はそんなことには頓着もせず、釣りは御鏡沼ときめていました。
田植えも終り、一段落した六月始めのある日、
空は晴れ湿気を帯びた風は青草をよぎり、魚の釣れる絶好の釣り日よりと、倉吉は勇んで御鏡沼へとやってきました。
しかし、今日は絶対釣れるはずとやって来た倉吉の釣り針には一匹の鮒も釣れません。
場所を変え、えさを変えても一向にうきは動きません。
釣れないままに、はて、どうしたものかと釣りの名人倉吉は考えもつかず、途方にくれて天を仰ぎました。
いままで晴れていた空は、にわかに黒雲がおおい、
沼は暗く、波はさわぎ雲を呼び、
数百年の老木は、ゴウゴウと枝をならし、すさまじい光景にどうすることもできず、
恐ろしさのあまりに倉吉は、呆然と立ちすくんでしまいました。
どれほどたっただろうか、
倉吉の耳元で 「倉吉さん、倉吉さん」 と呼ぶ声に、倉吉は吾に帰りました。
声のするほうに振りかえると、
それはなんと美しい花の精かと見まちがう美少女が、にこやかに倉吉へ話しかけてきました。
「のう、倉吉さん。あなたが毎日この沼に釣りに来ている姿をみて、
心丈夫な方とお見受けしました。
あなたを男と見込んで頼みたいことがあるのです。どうかお引き受け下さるまいか。」
と美しい声で問いかけてきた。
倉吉は心の中で、
このような深山のなかに、このような気高く美しい少女のいるはずはない、
これは多分大蛇の変化か、この沼の主の化身に違いないとおもいながらも恐ろしさのあまり、
「ハ、ハイ。私の身で出来る事なら、なんなりと仰せ下さい、お引き受けいたします。」
とおそるおそる答えました。
美少女は非常に喜んで語りました。
「はるか西の方に備前という国があり、その山奥三里のところに、
貝殻の沼という沼があります。
その沼辺に立って、
“クロンド、クロンド”と呼ぶと、クロンドという者が出迎えるはずです。
そのクロンドに、この状箱を渡してくれませんか。
その時、クロンドはあなたを自分の家に案内し、いろいろの物を、あなたにあげるはずです。
クロンドのもつ宝物の中に、“黄金の駒”というものがあります。
その駒を是非ねだり貰いうけて帰りますように」
と語り終わると、 状箱を手にもつ倉吉自身の姿に気がつきました。
倉吉は急いで家に帰り旅支度をととのえ、備前へと出発いたしました。
旅路は遠く、日かず重ねてようやく備前の国、貝殻沼に着きました。
それは山奥のものすごいところでしたが倉吉は沼の岸に立って
「クロンド、クロンド」 と呼びました。
呼び声はさざ波となって沼をわたってゆきました。
しばらくして沼の上に淡いけむりが立ちのぼると、そのなかから一人の美少年があらわれました。
それは気高く美しい少年でした。
倉吉は、美少年の近づくのを待って、あずかってきた状箱を渡し、尚も口上を伝えると少年は大変喜んで
「遠い旅路の使いご苦労様でした。
このお礼を申し上げたいので是非私の住居までご案内いたします」 と、
布をもって目かくしをし、美少年に背負われて沼の中に入っていきました。
ややしばらくしておろされると目かくしの布を取りはずされました。
それは、それは、きれいな御殿の奥座敷でした。
倉吉は見たこともない立派さに驚きながら見回すと、片すみの桐箱の上に安置されている黄金の駒をみつけました。
これぞまさしく美少女が
“是非ねだり貰い受けよ。 といった駒だ”と、心の中で大喜びました。
倉吉は、大変ご馳走になり、四方山の話しもつき帰ることになりました。
「遠い路のお使いご苦労様でした。
お礼としてあなたの所望するものを申しあげたいがお望みのものがあれば申されよ」
「あの桐箱に安置されている駒を」 と、倉吉はおそるおそる申しました。
すると美少年は心やすく倉吉に渡しました。倉吉は心の中で喜びました。
ふたたび目隠しをし、美少年に背負われ、沼の岸にもどり、やがて暇を告げ帰路を急ぎました。
長い旅でした。
やっとの思いで御鏡沼に戻ることができました。
早速、美少女に貝殻沼、クロンドの様子をすっかり話して、
黄金の駒を見せたところが、美少女は大変喜んで
「長い旅、ご苦労様でした。 その駒はあなたにあげましょう。 大切にして毎日米三粒ずつを与えて下さい。
そうすればその駒は三粒の黄金をうみだすでしょう」 と申しました。
倉吉は、美しい少女に深くお礼をいうと、家に帰り教えられたとおりに、毎日米を三粒ずつやりますと、三粒のふんをしました。
やがて、月日がたつにしたがって倉吉の家は富み、栄えその地方きっての長者となりました。
ところが倉吉は考えました。
一日三粒の黄金よりも一年分、数年分を一度に得る方法はないものか、
一度に巨萬の富を得て大長者になれる、それには米をたくさん食べさせることだと、
倉吉は早速一升ますにいっぱいの米を駒に食べさせました。
ところがどうしたことか駒は勇みたち 「ひひーん」 と、いななくと、大空へ飛び去ってしまいました。
やがて倉吉の家は、あとかたもなく亡びてしまいました。

それからしばらくすぎたころ、更科の荘のお百姓が、ある日一人で馬草を苅ろうと、山に入りました。
ところが、山のいただきに光かがやくのを見て、登ってみれば馬頭観音の尊像がありました。
お百姓は、家に帰ると村人にことのあらましを話しました。
更科の荘の村長は、村人と相談して、その山を厩嶽山と名づけお堂を建てて馬頭観音像をまつりました。
昔は、旧六月十六日の祭りになると、
会津地方のお百姓は、馬をつれて、源橋口・熊倉口・常世口から登り参詣をしました。