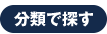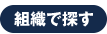「地域のアイディアや課題」がカフェの「メニュー」 「第2回オープンカフェばんだい」を開催しました!
「第2回オープンカフェばんだい」を開催しました!
「地域のアイディアや課題」がカフェの「メニュー」
地域の若者が気軽に集まって、やってみたいことやあったらいいなということを話し合う「オープンカフェ」(※)を2月10日(金)に、磐梯町公民館講堂で開催しました。
参加したのは、磐梯町在住の20~40代を中心に15名が参加しました。磐梯町の町民だけでなく、近隣の市町村と県外からのご参加がありました。
第2回のテーマは、「食べる・呑む」
・磐梯エリアに根付く商い 「お店を営む」
・無理のない商いの始め方 「商いをする場所」
・中山間地域の呑むを助ける 「地方の夜の移動」
「食べる・呑む」に関わる3つのテーマで、周辺地域で実際に取り組んでいるゲストを囲みながら、中山間地域でも、食に関する楽しみをどうやったら実現できるか、をそれぞれが取り組んできたことをシェアしたり、あったらいいなという想いを語り合ったりしました。

ゲストの皆さん

遠藤孝行さん (株式会社アウレ代表取締役・ななかまど食堂)
福島県福島市出身。東京でシステムエンジニアとして働いていたが震災をきっかけに2016年にUターン起業。会社運営を行いながらも猪苗代町地域おこし協力隊として3年間従事し、ふるさと納税推進・猪苗代湖環境保全・廃校利活用などを担当。アウレとしてはシェアキッチン運営・ICT教育支援・WEB制作などを行っている。

石井達也さん、汐里さん(農園GARA・wine&dining SOL)
達也さんはホテルマンから、汐里さんは料理人の前職から地域へUターンして就農し、農園GARAとして5年活動しています。『地域をもっと盛り上げたい、地域の人々の交流の場を作りたい』との想いで、「シェアキッチンななかまど食堂」にて期間限定(11月~1月)で「wine&dining SOL」として出店。地域に今まで無かったワインと洋食を提供しています。
藤井靖史さん(ばんだい振興公社理事、西会津町CDO、柳津町CDO、会津の暮らし研究室取締役、他)
「移動の自由を守る」をスローガンにした、浪江町、浜通り地域の住民や訪問者など誰もが利用でき、ワクワクする公共移動サービス、オンデマンド配車サービス「スマモビ」の事例についてお話しいただきます。
オープンカフェのルール
オープンカフェを開催するにあたり、アイディアを出しやすくするための簡単なルールを設けています。
- 人のアイディアの批判、否定はしない
- 「できない理由」じゃなく「できる方法」を見つける
- 「人、モノ、カネ」がなくても自分たちできることを考える
- 行政への要求の場ではありません
- 肩書きに縛られないフラットな場
- 温度差を楽しもう
3人のゲストトークを踏まえ、自分が興味があるテーマに分かれて、上記のルールの上、「やりたいこと」、「あったらいいな」というものを語り合い、それを「どうやったら実現できそうか」、「いいね!応援したい!」などのコメントをシェアし合いました。


今回は、磐梯町に愛着を持つ若い人が集まって、つながることを目的としていたため、具体的なプロジェクトの創出等をまとめるものではありませんでしたが、自分達の持つネットワークや場所とアイデアを組み合わせることで、実際にできそうなことも、たくさん発表されました。
<今後の予定> ※変更になる可能性もあります。
第3回 3月10日(金)
「オープンカフェ」とは※
「オープンカフェばんだい」は、コーヒーやデザートを楽しむ喫茶店ではありません。
毎回変わる開催テーマに沿ったアイディアや課題をみんなでシェアしながら、参加する皆が自分たちの手で磐梯の暮らしがより楽しくなるように自分達ができることを共に想像・考えていく場のことをさします。
例えていうなら、オープンカフェばんだいでは、ドリンクやデザートではなく、皆が持ち寄った「地域のアイディアや課題」がオープンカフェの「メニュー」になります。
磐梯町での暮らしを、「もっと楽しくしたい!」と思う、【まちに住む人】【まちに通う人】【まちのファンの人】が集まり、日々の暮らしがワクワクするものに変わっていけるように、自分たちの手でできそうなことを、みんなで話し合う場です。