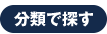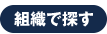「地域のアイディアや課題」がカフェの「メニュー」 「令和5年度 第6回オープンカフェばんだい「AR/VRを活用したまちづくり」を開催しました!
「令和5年度 第6回オープンカフェばんだい「AR/VRを活用したまちづくり」を開催しました!
地域の若者が気軽に集まって、やってみたいことやあったらいいなということを話し合う「オープンカフェ」を令和6年3月16日(土)に、磐梯町中央公民館講堂で開催しました。
参加したのは、磐梯町内外の小学生、30~40代を中心に22名(うち町内12名)が参加しました。
磐梯町の町民だけでなく、近隣の市町村や東京在住の親子の参加がありました。
第6回目のテーマは AR/VRを活用したまちづくり」 磐梯町では、昨年度から 、
・町内の文化財や観光資源を3Dスキャンしデジタル保存する「みんなで作ろう!バーチャル磐梯町3Dスキャンワークショップ」
・「バーチャル磐梯町 VR体験会」&アイデア創造ワークショップ などのイベントに取り組んできました。
今回は、VRを使って慧日寺や磐梯神社を楽しんでいただき、VR体験してみてどう感じたかを踏まえて、何ができるかのアイデアだし(ワークショップ)を行いました。
VR体験会では、バーチャル空間の会議室に入って、文字を書いたり、バーチャルの中で隣の人とハイタッチするなど、空間を超えたつながりを楽しみ、会が終了した交流会でも、延長して体験を続ける方も多くいました。
体験会を終えた後のアイデア出しでは、子どもたちからもたくさんのアイデアが飛び出し、今の技術でできそうなことから、これからこんなことができたら、というものまで、さまざまな企画に、共感したり、やってみたいという声が挙がったりしました。
ゲスト
秦 優さん(株式会社デザイニウム 取締役)

各種センサーを活用した体験型コンテンツを10年以上前から手掛けており、この数年はxRの中でも特にARでの体験創りを企画して、様々なプロジェクトを推進している。
西名清蔵さん(西会津町デジタル戦略プロジェクト推進マネージャー)

福島県富岡町出身。会津大学卒業後、都内でサーバーエンジニアとして従事。 東日本大震災を契機に南会津町にJターン。現在は西会津町のデジタル戦略室でプロジェクト推進マネージャとして町のデジタル化をサポート。VRに興味を持ったのは2018年から。以来、その魅力や可能性を様々な場面で紹介し、体験してもらっている。 最近の趣味は地域の中学生たちとポケモンカードで対戦する事。
オープンカフェのルール
オープンカフェのルール オープンカフェを開催するにあたり、アイディアを出しやすくするための簡単なルールを設けています。
- 人のアイディアの批判、否定はしない
- 「できない理由」じゃなく「できる方法」を見つける
- 「人、モノ、カネ」がなくても自分たちできることを考える
- 行政への要求の場ではありません
- 肩書きに縛られないフラットな場
- 温度差を楽しもう 2人のゲストトークの後、磐梯町で挑戦できる場所として、LivingAnywhere Commons会津磐梯、未日常、慧日寺資料館などについて、それぞれの担当者から場所や事例などを紹介いただきました。
その後、自分が興味があるテーマに分かれて、上記のルールの上、「やりたいこと」、「あったらいいな」というものを語り合い、それを「どうやったら実現できそうか」、「いいね!応援したい!」などのコメントをシェアし合いました。
今回は、磐梯町に愛着を持つ若い人が集まって、つながることを目的としていたため、具体的なプロジェクトの創出等をまとめるものではありませんでしたが、自分達の持つネットワークや場所とアイデアを組み合わせることで、実際にできそうなことも、たくさん発表されました。
「オープンカフェ」とは
「オープンカフェばんだい」は、コーヒーやデザートを楽しむ喫茶店ではありません。
毎回変わる開催テーマに沿ったアイディアや課題をみんなでシェアしながら、参加する皆が自分たちの手で磐梯の暮らしがより楽しくなるように自分達ができることを共に想像・考えていく場のことをさします。
例えていうなら、オープンカフェばんだいでは、ドリンクやデザートではなく、皆が持ち寄った「地域のアイディアや課題」がオープンカフェの「メニュー」になります。
磐梯町での暮らしを、「もっと楽しくしたい!」と思う、【まちに住む人】【まちに通う人】【まちのファンの人】が集まり、日々の暮らしがワクワクするものに変わっていけるように、自分たちの手でできそうなことを、みんなで話し合う場です。